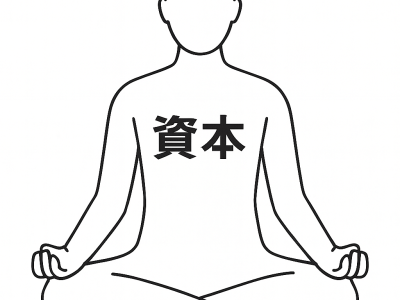「好き」と同じくらい、「苦手を避ける」ことも大切
子供の仕事選びに関して、先日「好き」を大切にしようと書いたのだが、それと同時に「苦手を避ける」視点も同じくらい重要だよなーと思ったので、それについて。
「好き」を大事にするも、「苦手」を避けるも。これはどちらも、仕事を長期的に捉える視点から来ている。これは、仕事が長期スパンでの話になるので、瞬間的な効率ではなく、積み重ねることで効果が大きくなる「複利」の観点でもある。「好き」であれば、長く続けることが苦にならない。「苦手」を避けることで、パフォーマンスを落とさずにすむ。どちらも、自分の力を最大化するための大切な戦略。
限られた時間とエネルギーを使うなら、好きなこと・得意なことに注ぐほうが、リターンは確実に大きい。苦手なことに時間をかけすぎると、成果が出づらいだけでなく、心身ともに疲弊してしまう。もちろん、仕事である以上、好きなことだけをやるのは難しい。だが、苦手なことにかかる時間やコストを、可能なかぎり削減する工夫はできるはずだ。
数字が苦手な私
たとえば私は、月末の経費精算や予算集計のような作業が非常に苦手だ。どれだけ時間をかけても、なぜか数字が合わない。もし自分が銀行や経理の仕事をしていたら、おそらく毎日がストレスで、いずれ心を病んでいたかもしれない。だからこそ思う。「苦手なことを主戦場にしない」というのは、自分の人生を守るためにもとても大事な考え方だ。
それでも多くの人が、社会的評価や報酬の高さに惹かれて、「本当は苦手な仕事」を選んでしまうことがある。でも、それは大変な道だ。本当は、自分が「普通にできること」で誰かに喜ばれることが、自分にとって自然だし、力を発揮できる場所なのに。私は、幸い、そういう道に行かなかったのだが、結構ついてたな、と思う。
「分業社会」と「ハッピーな世界」
当たり前のことを言うのだが、今の社会は分業によって成り立っている。そして分業の本質は、「それぞれが得意なことを担うことで、全体の効率が上がる」という点にあると考えている。あなたの得意と私の得意の交換。分業で大事なのは、自分は自分の「得意」を担い、「苦手」は他者に任せる。それが巡り巡って、社会全体をより良くすることにつながる、そんな感じ。
真逆は、みんながみんなそれぞれの苦手なことをやる状況だ。それはディストピア感もすごいし、全体の生産性が、著しく低い社会だろう。だから、それぞれが好きなことをやるというのは、社会全体からみても、それは理にかなったことなんだと思う。なお、好きなことをやると、好きにやるは全然別なので、念の為。
「好き」と「得意」に投資しよう
仕事は、一時的な勝負ではない。10年、20年と続いていくマラソンのようなものだ。だからこそ、何に時間と力を投資するかの選択は、とても重要だ。「苦手を避ける」「好きに集中する」─そんなシンプルな方針が、実は長い目で見たとき、最も確実で、最も人を幸せにする道ではないだろうか。
ただ。子供達よ。だからと言って、苦手な科目をやらないとかはやめよう。苦手苦手という代数、もしかしたら好きになるかもしれないよ。中学生や小学生の君たちくらいの年齢で、それを判断するのはちと早い気がするからね。
学生時代、私は英語が苦手で大嫌いだったけど、ある時、ちょっとしたコツを知ったら、「なんてわかりやすい科目なんだ!」となった。大人になってからの苦手や好きはあまり変わらないけど、子供の時のそれは結構変わったりする。そういえば、子供のころ苦手だった食べ物は、今大好物だったりする。ということで、子供の仕事探しの話は、「長期的には好きへの投資。短期的にはいろいろやってみる」が、いいのでは?というのが、今回の結論。
この記事を書いたのは
- 鈴木 康孝
- シックスワン株式会社。マーケティング&プロモーション領域担当。クリエイティブとかアイデアとか好き。尊敬する人、村上春樹さんと永井均先生と佐藤雅彦先生。今年の目標は、プログラムと英語をちゃんとやること。サウナと交互浴が大好き。