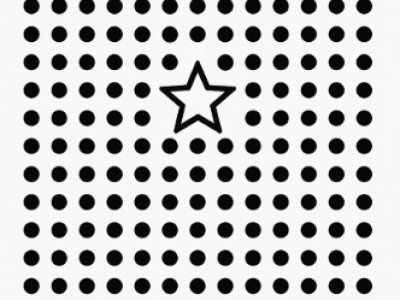最近、調査のためにあるブランドの検索結果を確認する機会があった。すると、競合他社のブランドがリスティング広告を出稿している場面に遭遇した。今日はこの点について考えてみたい。例えば、自社のブランド名(A)で検索した際に、競合他社であるB社やC社がといった競合の広告が出ているといった事象のことだ。
掲載停止を聞いてくれない企業も
これは、Googleの自動入札や広告露出ロジックによる部分もあるようだ。特別な設定がなければ、Googleが“良かれ”と思って広告を表示してしまう可能性もあるようではある。このあたりの挙動は完全には把握しきれていないし、いくらでもいいわけができる領域のようではある。しかし、問題は「その会社に掲載をやめてほしいと指摘をしても、やめてくれない事」があるという点だ。
業界としては、暗黙の了解としてブランドリスティングは控えるという“紳士協定”的な習わしがあるとも聞く。しかし現実には、それに応じない企業も一定数存在しているようで、Google検索でも「他社ブランドに広告を出されて困っている」「法的拘束力はないのか」といった声が散見される。
どうやら広告文内に競合の名称を直接含めるのはNGであるものの、競合ブランドワードへの出稿自体はGoogle上で禁止されていないようだ。だが、私が問題視したいのは、「出稿できるかどうか」ではない。それを選択してしまう思考そのものが、成長を阻害しているのではないか?という点だ。
短期的な“効率”のワナ
他社ブランドへのリスティングは、単価が安く、獲得効率が良いことがあるかもしれない。ロイヤルティの高いブランドファンを奪える可能性は低いとしても、一定の流入や獲得は見込めるのだろう。だからこそ、経済合理性において“成立”してしまう。
しかし、それこそが問題なのではないか?と。リスティング広告全体に言えることかもしれないが、お金があれば勝てる“札束の殴り合い”構造になっている。特にブランドワードではその傾向が顕著だ。もちろん、改善すべき点は多くあるが、ここだけに注力しても競争優位性は構築されない。特に、ある程度フェーズが進んだプロダクトやサービスにおいて、リスティング広告が主要な集客手段であり続ける状況は持続性に欠けると私は思う。
限られた広告予算をどこに使うか?
競合ブランドワードへの出稿の本質的な問題は、それが全体のごく一部であったとしても、限られた広告費と労力を“他人の畑”に向けたプロモーションに投下している点にあると思っている。
同じリソースを、自社ブランドの強化やサービス改善に投資すれば、中長期的には圧倒的に効率的だと考える。仮に短期的なCPAが多少悪化したとしても、競合ブランドへの出稿は選択すべきではない。なぜなら、それはマーケティングとしての戦略的思考を欠いた行為であり、“自社ブランドの未来を食いつぶしている”ようなものだからだ。
さらに言えば、そうした出稿やその戦術が、表に出てしまえば、企業のセンスや品格が問われるようにも思う。ブランドワードに広告を出すことをやめてほしいと「メールをしても、電話をしても、出稿をやめてくれない企業もある」といった話も聞く。ここで具体名を挙げるつもりはないが、そうした企業は長期的に見て厳しい結果を招くのではないかと感じる。
広告費は重要なリソースだ。だからこそ、“目の前の数字”に惑わされず、自社のブランド価値を育てる方向に投資することが、長い目で見たときに最も大切なマーケティングのあり方なのではないだろうかなと。
この記事を書いたのは
- 鈴木 康孝
- シックスワン株式会社。マーケティング&プロモーション領域担当。クリエイティブとかアイデアとか好き。尊敬する人、村上春樹さんと永井均先生と佐藤雅彦先生。今年の目標は、プログラムと英語をちゃんとやること。サウナと交互浴が大好き。