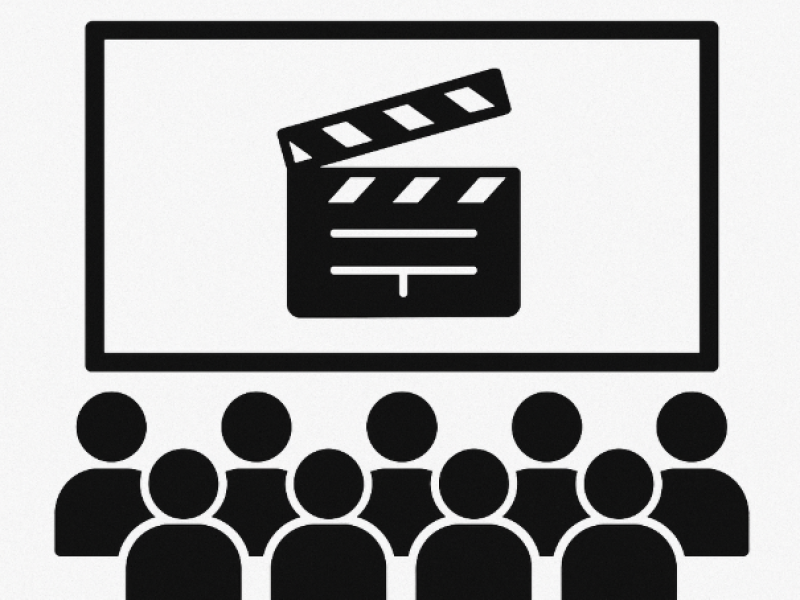近年、「カメラを止めるな!」や「侍タイムスリッパー」といった作品が全国展開し、ミニシアターから大きなヒットにつながるケースが増えている。ミニシアターという場所は以前は「お金が動かない世界」だったと思うが、今は、当たればしっかり収益を生み出すビジネスになってるように思う。これはネットの影響を抜きには語れないだろう。ネットの良い面だ。
さて。ミニシアターといえば、私が住む街、阿佐ヶ谷にもある。Mork阿佐ヶ谷。散歩しながら立ち寄れる距離にあり、とても貴重な存在だ。「ちょっと2時間、時間があいたから映画みよかな」そんなことができるのは、Mork阿佐ヶ谷のおかげだ。
先日、そのMork阿佐ヶ谷で観た「北浦兄弟」という映画がとても面白かった。1週間限定の上映だったが、2回足を運んだ。作品そのものも良かったが、上映後の監督やプロデューサーによるトークセッションがさらに印象に残った。主演俳優自身がプロデューサーを兼ねているということもあり、最後まで聞き入ってしまった。
この映画、構想から上映までに4年を要したという。登場人物は少なく、1週間ほど民家を借り切って泊まり込みで制作。俳優たちが自前でスタイリストや料理まで担当したそうだ。手作り感のある現場で、一本の映画が「プロダクト」として形になった。
この4年間という制作期間中、映画自体は利益を生んでいない。俳優や監督、プロデューサーはそれぞれ別の仕事をしながら生活をつなぎ、このプロダクトを完成させたのだろう。ヒットすれば、一気に環境は変わる。私は映画というビジネスをハリウッド大作の文脈で考えることが多かったが、ミニシアター系の映画もまた同じ構造を持っているのだと実感した。
よく考えれば当然だ。映画だけでなく、小説や料理も「プロダクト」であり、それを使って人々はビジネスを営んでいる。ブランド戦略やプロモーションも不可欠で、映画のエンドロールにも宣伝やPRの担当者名が記される。作品はひとつのビジネスとして多くの人を巻き込み、成功すれば分配が生じる。
私は普段、プロダクトというと、ウェブサービスのようなプロダクトを中心に考えがちだ。しかし、小説は一人でも作れる低コストのプロダクトであり、映画は複数人が関わる高コストのプロダクトだが、当たれば大きなリターンがある市場だ。構造は異なっても、本質は同じ「プロダクト」である。
ところで。新宿の映画館「シネマカリテ」閉館というニュースをきいた。シネマカリテを保有するのは、上場企業である。だから、ビジネス判断の結果なのだろう。だがこうした話を聞くと、一観客として応援すべき映画館や作品を意識的に支えていかねばならないと思う。映画と出会う場所としての映画館は欠かせない。
最近は、若い人が映画館に足を運んでいると聞くが、ミニシアターという存在を大切にしていきたい。
この記事を書いたのは
- 鈴木 康孝
- シックスワン株式会社。マーケティング&プロモーション領域担当。クリエイティブとかアイデアとか好き。尊敬する人、村上春樹さんと永井均先生と佐藤雅彦先生。今年の目標は、プログラムと英語をちゃんとやること。サウナと交互浴が大好き。