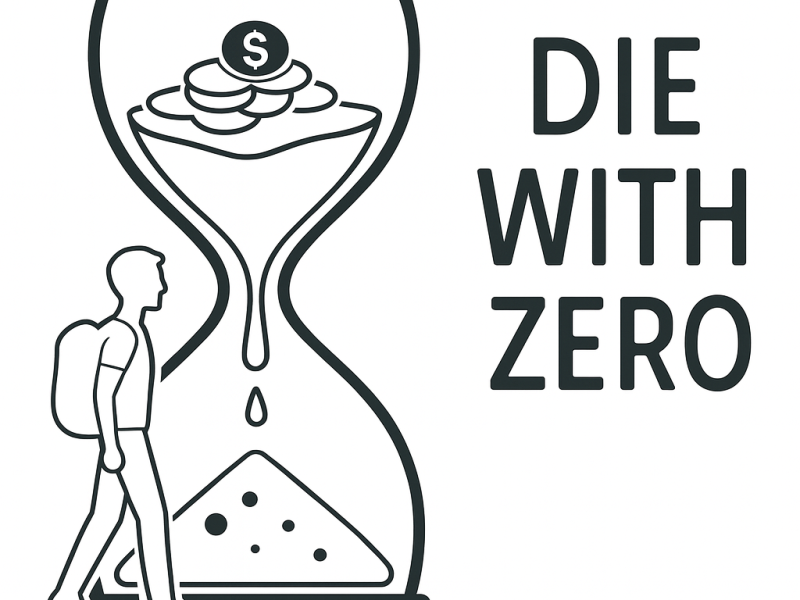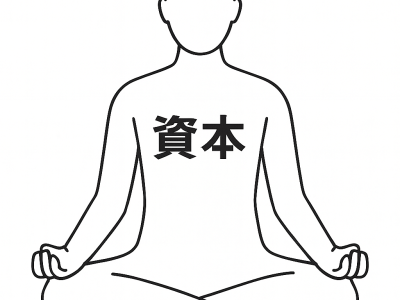ビジネス経験が豊富な先輩がいます。そのある方に『Die with Zero』という本を紹介したら、とても喜ばれました。理由はシンプルで、もらった一言が、印象的でした。「こんな観点、誰も教えてくれなかった」そう言われたのです。今まで、ビジネス系の本を紹介して、良いと言われた事は皆無だったのに、です。
なぜこの本が、長年ビジネスの第一線で戦ってきた人の心を動かしたのか。その理由を考えると、企業と個人の“生き方の軸”の違いがあるなーと思いました。
企業の右肩上がりと、個人の幸福曲線
企業は常に成長を求められます。今年より来年、来年より再来年。売上も利益も右肩上がりでなければならない。これは上場企業ならなおさら、株主や市場からの期待によって強く刷り込まれる考え方です。
ところが、この企業的な成長曲線をそのまま個人に当てはめるとどうなるでしょう。典型的なのは「死ぬときが一番金持ち」という現象です。稼ぐことをやめられず、お金を使うタイミングを失い、人生の終盤に最大の資産を抱えたまま去っていく──。数字としては立派ですが、幸福という観点ではどうでしょうか。
『Die with Zero』が提案する時間軸の転換
この本の主張は明快です。「どこかの段階で稼ぎのピークを設定し、その後は意識的に使っていく」。それも、老後の余生を待たず、できるだけ早く経験や喜びに変えることが大切だと説きます。もちろん、仕事を突然やめることを推奨しているわけではありません。むしろ好きな仕事なら、趣味や自己実現の一環として続けるのもいい。しかし、「働き続けなければ不安」という発想や、「老後のために貯めることこそ正義」という固定観念を一度疑ってみよう、という提案です。
法人のKPIと個人のKPIは違う
あらためて面白いな、と思ったのは、企業と個人のゴールがまったく違うことです。
- 企業のKPI(評価指標)は売上や利益。
- 個人のKPIは、経験や充実感、家族との時間など、“幸福の総量”です。
企業では、従業員の満足にお金を使う場合でも、それが利益や成長に結びつくときに限られます。目的はあくまで売上と利益です。一方で、個人にとっては「どう使って、どう幸福になるか」が目的そのもの。ここに大きな断絶があります。
二重のライフサイクルを意識する
だからこそ、法人に所属しながらも、自分の人生の“幸福曲線”を意識して設計することが大事になります。
- 稼ぐ時期:法人というプラットフォームを活用し、スキルや収入を伸ばす
- 使う時期:経験や喜びを最大化するために時間と資産を投下する
この二つのライフサイクルを意識的に区切ることで、企業的な右肩上がりの論理から自由になり、人生のKPIを自分で設定できるようになるなと。これは今は従業員視点ですが、経営者の場合、この両者が重なってしまうので、注意が必要ですね。
『Die with Zero』は、お金の使い方の本であると同時に、人生の評価軸を変える本でもあるのかもしれないです。役員が「こんな観点は初めて聞いた」と言ったのは、法人の成長論理の中では決して出てこない言われない視点だからかもしれません。
法人や企業は、自分の死後も永遠の成長を願うものだとは思います。ゴーイングコンサーンが前提だから。でも、個人だと、そういうものでもないですからね。もちろん子供や家族のことは思うけど、それはその人たちが考えることでもあるので。
DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール
https://amzn.to/460BFRK
この記事を書いたのは
- 鈴木 康孝
- シックスワン株式会社。マーケティング&プロモーション領域担当。クリエイティブとかアイデアとか好き。尊敬する人、村上春樹さんと永井均先生と佐藤雅彦先生。今年の目標は、プログラムと英語をちゃんとやること。サウナと交互浴が大好き。